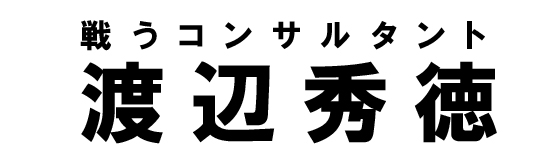シーズ志向かニーズ志向か。どちらを選ぶ?

ちょっと専門的な話になってきますが、冒頭にお伝えした、シーズとニーズについて。
シーズ(Seeds)とは、企業が持っている新しい技術・材料・サービスなどのことで、世の中にないビジネスの「種」です。
人々に新しい価値を提供し、ビジネス構造すら変える可能性を持っています。
シーズは、世の中の問題を解決する新しいものであることもあれば、必要性のあるものではないけれどライフスタイルを変革したり、新しい驚きや感動を与えて人々に必要とされるようになるものもあるでしょう。
iPhoneはまさに、「シーズ」にあたります。
対して、ニーズ(Needs)とは、消費者が求めているもの、つまり「需要」です。
この場合、消費者が欲しいものは明確です。
分かりやすく言うと、食品・車・家電など。
これらは、世の中に当たり前にあるもので無いと困りますよね。
いわゆる「調査」でわかることのほとんどは「ニーズ」だと言えます。
企業によって様々な戦略がありますが、大きく分けてシーズ志向とニーズ志向の二つがあります。
■シーズ志向
世の中に新しい価値を提供して、市場を自ら作っていくスタイル
■ニーズ志向
すでに顕在化しているニーズを満たす商品を作り、市場へその商品・サービスの優位性をアピールして売るスタイル
例えばiPhoneを開発したAppleや「ググる」を生み出したGoogle等は、新しい価値を作ることでビジネスを拡大している企業です。
「Google Glass」や「自動操縦車」などの開発は、シーズ志向の分かりやすい例ですよね。
ニーズ志向のビジネスをしている企業では、例えば、低価格の家電製品を作っている中国企業などが当てはまります。
すでにニーズのある家電を競合よりも安く、高機能・多機能等付加価値をつけて売っていく企業です。
シーズ志向の企業には、世の中の流れを読む力、新しい時代を作るマーケティング力、新規開発に回せる経営資源(人・モノ・金)などが必要になります。
大きな資金がかかるので、回収するまでにも時間がかかります。
ただ、市場を独占したり開拓者として優位なポジションを維持できたりするので、新規事業開発として取り組む企業も多いでしょう。
ニーズ志向の企業には、今よりももっと良いものを提供できるアイデアや改善力が必要です。
基本的には基礎研究や新規開発投資の資金が必要ではないため、売上と利益を作りやすいビジネスであると言えます。
現代は、ネットの発達とグローバル化で世界中から資金を集められる環境が整っているため、シーズ志向で立ち上げられた企業が一気に大企業となることも増えていくと思います。